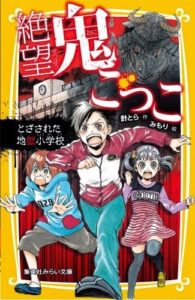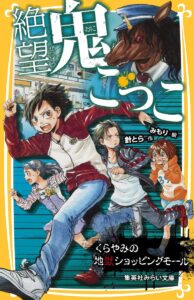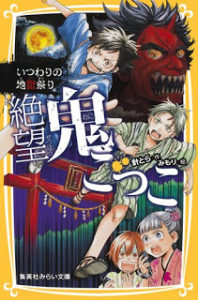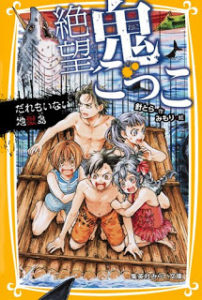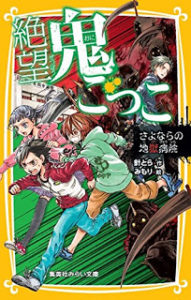無料キャンペーン中にXでつぶやいていた、チョイ裏話を公開してるよ!
ネタバレも混じってるので注意!
和也と孝司ですが、じつはプロット段階では出ていません。最初の犠牲者として登場する、その場かぎりのキャラのはずでした。書いてみたら、なぜか章吾と一緒に漫才をはじめたので、そのまま2巻以降も章吾にまとわりつくことに…。そのまま20巻以上経った今も出てくる準レギュラーになったとさ…
ちなみに章吾の方はプロット段階で出ていましたが、初期プロットでは、嫌なやつ――マルフォイポジションでした。
でも僕が嫌なやつを書くのが苦手で考えあぐねていたら、打ち合わせで「もういっそ一緒にキックじゃね!?」というノリに…。良きライバルキャラになったのでした。
1巻といえば、牛鬼が大翔たちを追いかけてくるときに歌ってる替え歌は、はじめは「うさぎとかめ」ではなくて、「森のクマさん」でした。(アルーヒ- モリノナカ- オニサンニ- デアァッタ-)
権利関係でちょっと微妙だったので差し替えたのだけど、作者が1巻で一番自信があったのがその「牛鬼の森のクマさんミュージカルシーン」だったので、結構ショックだった記憶。
鬼さんの〜 言うことにゃ〜 お嬢さん〜 お逃げなさい〜 に葵が返答で歌ってノリツッコミしてたの…。…うん、なんだそのホラー小説…。
そして、ツノウサギもプロットには出ていません…というか、初稿段階では鬼たちも、替え歌を歌ったりしない、ホラークリーチャーっぽいやつらでした。
初稿を読んだ担当に「鬼のキャラ立てて」と言われた結果、鬼たちが歌いはじめ、ツノウサギがピョンピョンする事態に…。
担当は、「いや、こういうのは想定してなかった…」という反応だったのだけど、僕は「めっちゃ俺っぽい小説になった!」と手ごたえを感じたので、そのまま通させてもらったのでした。
ツノウサギがいなかったら今の絶望鬼ごっこはないと思うので、良かったなぁ…と。
2巻『くらやみの地獄ショッピングモール』のチョイ裏話!
なぜ2巻の舞台がショッピングモールになったかというと、ご存知、ゾンビ映画の古典「ゾンビ」(1978)の舞台が、ショッピングモールだからです! 担当がゾンビ映画好きで、ゾンビだ! → ショッピングモールだ! と(適当)。僕もいくつかゾンビ映画観てみたのだけど、血みどろ系はニガテかな~。
ちなみに「ショッピングモール」に決まる前は「修学旅行」でした。修学旅行に出掛けた大翔たちの前に、地獄の暗殺者・影鬼くんがあらわれ、人の影の中に隠れる彼を相手に、日暮れをタイムリミットに影踏みバトル! …怖くないということでボツになったのだけど、影鬼くんはあとの巻で出てきます。
今巻は、「ともかく怖くして」というオーダーでした。でも、実はこれって難しい。ホラー映画の続編が難しいのとおなじ理由で、続編になると怖さって減っちゃうんですよね。慣れるので。エイリアンのようにアクションに振ったり、SAWのようにどんでん返しに振ったり、怖さ以外の軸が必要だなと。
そんなわけで2巻では、「ギミックの面白さ」に振っています。どんなものでも出てくるショッピングモールバッグ、落下エレベーターでのクイズ大会、地下食品売り場でのタイムセール(お客は…)など、ショッピングモールを活かした賑やかさが特徴の巻となっています。
ちなみに、初稿でのクイズ問題は、出版時と全然ちがっていたり…。
せっかくなので、ちょっと抜粋します。↓↓
『問題です。マンガ“ドラゴンボール”で孫悟空が亀仙人から教わった技は――』
大翔と悠は腰だめに手をかまえる。
『――かめはめ波ですが、孫悟飯がピッコロから教わった技は?」
「「魔閃光ッ!!」」両手を額にかざしてから、2人でボタンを押しこんだ。
『問題です。“シャンデリア”って10回言って?』
「「「シャンデリア、シャンデリア、シャンデリア、シャンデリア、シャンデリア、シャンデリア、シャンデリア、シャンデリア、シャンデリア、シャンデリア!」」」
『では、童話で毒りんごを食べたのはだれ?』3人は声をそろえて元気よく拳をつきだした。
「「「シンデレラッ!!」」」
……うん。ボツでした。
こ、怖くしろって言ってんだろぉぉ!!
3巻『いつわりの地獄祭り』のチョイ裏話!
絶鬼ははじめ、シリーズを想定してなくて、1巻は1冊完結、2巻はとりあえずもう1冊、くらいのつもりで書いていました。 3巻から本格的にシリーズ化を意識し、キャラクターを掘り下げる巻となっています。
1巻が出たあと、予想外に「荒木先生どうなったん…?」という声が多かったので、この巻は、荒木先生の巻! となりました。 いなくなっていた先生が帰ってきたけど、前と様子がちがう…どういうことだ…? という謎を追っていく、ちょっぴりミステリホラーな巻となっています。
ちなみに杉下先生はプロットには登場しておらず、はじめはほんとに足をケガしただけの、体育の先生として登場していました…! 名字にあまり特徴がないのも、モブだったから…。当初は2巻につづいて青鬼くん(という名前はまだなかったんだけど)が出てくるのかなと思ってたんですよね。
それが、大翔が鬼から逃げてるシーンを書いてる途中、横槍がどうも陰湿で、「あ、これはほかに誰かいるわな…」と思って見回したら、ニコニコ笑って出てきた…という感じです。
「言われたからじゃなく、出てきたいから出てきただけ」。
登場時からそんな方でした。青くんは横入りされたのだ…(涙)
ちなみに荒井先生に取り憑いた赤鬼は、黒鬼とケンカして負け、罰ゲームのような感じで取り憑かされています。3巻時点では凶悪なのですが、もともとの性格はただのケンカ好き。長く荒井先生に取り憑いているうちに……とそのあたりの事情は、17巻 富士の樹海編にて!
ちなみに針とらが3巻で好きなのは、お神輿ワッショイのシーンです。彼らは、そこに鬼がいるとか子供が逃げているとか、そんな事情は知らんのです! ただ、江戸っ子漢の熱い魂でもって、神輿を回しているだけなのだ…!
4巻と5巻はまとめて考えた話で、ざっくり「鬼の正体がバレるまで」と「鬼の正体がバレたあと」のお話になります。4巻は、バレるまで! ということでこの巻は、サスペンスの巨匠・ヒッチコックの、「テーブル下の爆弾」という考え方を用いて構成しています。
どういうことかというと、テーブルの下に隠された爆弾が、登場人物にも観客にも知らされずに突然爆発したら、一瞬のサプライズしか生じない。でも、テーブルの下の爆弾が、登場人物には知らされないが、観客にはあらかじめ知らされているとき、爆発までの間、サスペンス(どうなっちゃうの!?)が成立する…という考え方ですね。
なのでこの巻は、「読者にはあらかじめ鬼の正体が知らされているけど、大翔たちにはわからない」という組み立てにしました。「そいつ! 鬼そいつ…!!」という読み味にしたく。 もう児童書ということは忘れているな…。
なので、「主人公たちには、あなたのことはヒミツにしててね…」と鬼に頼んだら……あの御方、調子にのりはじめやがってですね…。隠してることにウキウキしたのか、子供を騙したり弄ぶのが楽しくてたまらない…! という、性格最低オンステージとなりました。 こいつ児童書にいて大丈夫なんか…。
そんなヤベェのが暴れるなか、児童書としてのテーマは、「大翔と悠の友情」です! 真っ当だ! 大翔と章吾は少年マンガ的なライバル関係が強いのですが、大翔と悠については、等身大の「友達」という感じがあって、僕はこっちも好きだったりします。大翔にとって、悠の存在は大きいんだろうなと。
最後にこの巻で一番好きなセリフは、
「先生ね。常に真剣に子供と向き合うのが、教育者の務めだと思ってます。ゲームだって、子供の遊びだとバカにしない。真剣にやる」
「なので、ルールどおり、ほんとに処刑します。みんなも、遊びだからと気を抜かず、真剣に死を覚悟してください。いいですね?」
ある意味、一生懸命なヒトなんです…(?)
第一部のときは、鬼ごっこのいろんな遊び方を調べながら、内容を考えることがたまにありました。「ことろことろ」「ケイドロ」とモチーフに使ったので、ほかになにかないかな~と調べていて、これにしよう! と思ったのが、「増え鬼」です。 鬼がどんどん増えていく鬼ごっこ。 別名、「ゾンビ鬼」。
そんなわけでこの巻は、ゾンビのごとく、大量のオニに襲われる鬼ごっこになりました。 しかもその鬼はこれまでの鬼ではなく、鬼にタッチされちゃった(?)、クラスメイトや校長先生たち。見知った人たちに追いかけられるということで、ちがった怖さを目論んだ巻になっています。
ちなみにオニになった人間たちが相手の巻はもう1つあって、20-21巻になります。5巻では同学年の子供たちが相手でしたが、こちらでは、一番オニになってほしくない人間たちが…。 こちらもぜひチェックしてみてね!
ちなみに5巻は書きながら結構方向性を変えていて、はじめは、「大量のオニとサーチライトが照らすなか、監視をかいくぐって校長室に向かう、『メタルギアソリッド in 小学校!』」みたいなイメージでした。(メタルギアソリッドを知らない人はググってね)
オニとなってここぞとばかりに威張る先生がいたり、オニになれなかった担任の先生に騙されそうになったり、クラスメイトの性格分析で進行ルートを決めたり……本に収録されていないシーンが結構あります。
校門の見張りに立った先生たちを見て、大翔たちが作戦を話し合うシーンがこちら… ↓
「強行突破できないかしら?」
葵が考え考えいった。
「校長先生と教頭先生くらい、2人でガツンとできるんじゃない?」
先生たちが正気を取り戻して聞いたら、泣きだしそうな案だ。
「2人でって、それは、ヒロトとアオイで?」
「大翔と悠で。先生たちをガツンとやるなんて、そんな野蛮なこと女子にできるわけないでしょ?」
「ぼくにだってそんな野蛮なことできないよ」
「じゃあやっぱり、大翔しかないわね。校長先生と教頭先生をぶん殴ってきて、大翔」
「まかせたよ。校長先生と教頭先生をぶん殴ってきてよ、ヒロト」おまえら、おれをなんだと思ってるんだよ。
……いつもどおりだ。
クリーチャーとしての鬼とはちがう面白さを出したかったのだけど、いまいち怖くならないということで、このへんはカットして、ボスとの対決シーンが厚めの構成となりました。
ひたすら鬼に追い詰められ、力尽きていた当時の針とらさん。
針「フルタイムで働きながら(当時)、書き続けるのキツイよう! 南の島にでもバカンスに行きたい…!」
担当「じゃあ南の島に行ってもらいましょうか。…大翔たちに!」
針「…俺は!?」
…というやり取りがあったというのは冗談ですが、これまでと違うことをやってみたいなと思い。作中でもそろそろ夏休みだし、思い切って遠くの場所を舞台にしようということで、離島に遊びに行く巻になりました! 島の名前が七里島なのは、取材で八丈島に行ったから…。海がきれいだった!
この巻のテーマの1つは、『不条理な鬼ごっこ』!
黒鬼が登場してから、策略とがっぷり組み合う展開が多かったため、ひさしぶりにひたすら理不尽に鬼に追われる話にしたいなと。
そんなわけで、島は生き物が軒並み鬼の、モンスターアイランドになってしまいました…!
もう1つのテーマは、『ひと夏の淡い恋』!
当時担当が、「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない」というアニメに感動した、という話を聞いていて、あ、そういうのも新鮮でいいよな! と思い。
君と夏の終わり 将来の夢 大きな希望 忘れない 10年後の8月 また出会えるのを信じて…
そんなわけで、『ひと夏の淡い恋』×『不条理な鬼ごっこ』な巻となりました! 酷い食い合わせだな! 夏の離島での子供たちの楽しいやりとりや、無人島サバイバル生活、ふしぎな女の子に、巨大甲虫カブトVSクワガタバトル! など、にぎやかで楽しく、ほんのり切ない巻になったかなぁと思います。
そして、児童書で「無人島で子供たちだけで生活」。これはもう、火をつけるのに苦労したり、食料を調達するのに四苦八苦したり、文明の利器がない状況ならではの、サバイバルの苦労や楽しさを描かなければならないでしょう! というわけで、石斧やイカダを作ったり、釣りをしたりすることに!
でもエサのミミズは鬼ミミズだし、釣れた魚は鬼ザカナだし……あげく苦労する大翔をよそに、ライバルは、やってみたらできたが? というノリでイカダを完成させているのでした。 これだから…! これだから天才は…! もっと苦労しろ…!
もうひとつ、遊びの路線からは、「ことろことろ」「ケイドロ」「増え鬼」ときて、今回は「だるまさんがころんだ」を取り入れています! 直径100メートルの鬼のテリトリーを、だるまさんがころんだで乗り越えて進め! このシーンは勢いがあって好きです。ヤツも乱入します。
作者がこの巻で一番お気に入りのシーンは、崖崩れに巻き込まれて絶体絶命の大翔が、カブトとクワガタの勝負の行方を気にしてるところ……です…! 小学生男子なので…!
ちなみにじいちゃんが大翔たちに毎年遊びにくるよう画策した甲斐あって(?)、つぎの年も大翔たちは七里島に遊びにいっています。 でもそのときはトラブルで島に着けず、不思議な村へ泊まることに……と、こちらエピソードは13弾、『とらわれの地獄村』でお楽しみください!
前巻で、南の島へバカンスに行って、楽しかったな! そんじゃ、読者を刺しにいくか! 背中から! …そんな巻になります。
病気のお母さんの先がもう長くないことを知った章吾の前に、鬼がやってきて、運命を変えないか、と誘いを持ちかけるところからはじまるこのお話。 人の強い願いに悪魔が取引を持ちかけるのは、ホラーの定番です。 章吾はそこで即断をせず、大翔たちに相談しようとするのだけれど…?
この巻は、「友達を頼ろうぜ!」という大翔たち側が引き寄せる流れと、「一人で修羅の道をいけ」という鬼側の引き寄せる流れの狭間で、章吾が揺れ、孤独を囲っていくお話です。 鬼に狙われてハラハラ…というより、章吾と大翔たちのあいだの関係に、緊張と亀裂が生じていくお話になっています。
書く前は、児童書として、商業としてアリなのか…? とやや躊躇しました。 児童文庫は明るく楽しいのが基本…という考え方はあって、僕は「男の子が読むなら、主人公を追いつめるタイプの作劇の方がよかろう」とサスペンスに振ってやってきたけれど、これは追い詰める種類がちがうんですよね。
物語の中で傷を負うのは子供時代に大事なことじゃないかな、それがフィクションの役割だろう、という思いもあったのだけど……商業の枠の中で書く以上、そのへんは版元の考え方次第。 迷ってたのだけど、むしろ刺せ!心臓を!👹みたいに言われたので、遠慮なく刺しにいきました。
結果的に、読者にも受け入れてもらえたようで、みんなついてきてくれるんだな…とちょっと感動した記憶。 作り手が勝手に日和っちゃだめですね。 このあたりから、絶望鬼ごっこは、「鬼に追いかけられる話」だけでなく、「鬼のもとへ行こうとする友達を追いかける話」になっていきます。
「あたしもたくさん調べたけど、死神を倒す方法について、信頼できる情報はみつからなかった。まさか、人間に恋させることだ、なんていわないでしょう?」
「そのマンガは俺も好きだが」